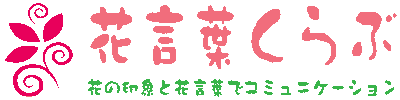でも、桜っていつ見ても綺麗だな~

今はお花見と言えば桜だよね。でも、江戸時代までのお花見は桜の花じゃなく梅の花だったんだよ。ためになるだろ~

どなたか存じませんが面白いお話ありがとうございます。
知り合いにも教えてあげたいので、なんで梅から桜になったのか教えてください。

合コンにも使えそうなネタだろう!?(・∀・)
ソメイヨシノのあれこれ含めて説明していくから記事を読むんだな

おねがいしゃすぅぅぅぅぅぅ
お花見に使われる花が桜になったのは?

今は、花見と言えば桜以外考えられないと思う人がたくさんいると思います。それほどまでに日本人にとって桜はなじみ深い花です。国としての花にもなっていますし、外交で使われたりもしますもんね。
でも、時代をさかのぼってみると実はお花見で使われていた花は桜じゃない時代があったんです。
その時代は、大仏などのイメージが強い奈良時代です。その当時桜を差し置いて人気だった花はピンク色の花が美しい梅の花です。
なぜ梅が使われていたかというとそれは、奈良時代の貴族たちが家の庭などを造園する際に梅を入れることが流行っていたそうなのです。そのため広い庭でお花見をしていた貴族たちが見る花は梅になったようです。
また、中国との貿易が盛んだった時代でもあり、中国では梅が大変人気だったことも日本の貴族の梅ブームに一役買っていたようです。
その頃は今よりもずっと桜は神聖な花でなかなか利用しづらかったのかもしれません。しかし、平安時代に遣唐使を廃止したことにより中国の梅の猛烈プッシュがなくなり日本独自の花見文化が浸透したようです。
そのため、神聖な桜を眺めながら食事をする今の花見文化が平安時代にできていったようです。
ソメイヨシノの花言葉

ソメイヨシノの花言葉は「純潔」「優れた美女」といわれています。
ソメイヨシノに上記のような花言葉が付けられた理由としては、古来より愛されてきた桜の代表種であるソメイヨシノがその美しさから女性にたとえられていたことが由来です。
確かに春先に河川敷に広がるピンク色の景色は美しい以外の言葉が思いつかないですよね。
ソメイヨシノの名前の由来は?
ソメイヨシノの花名の由来は江戸時代の末期ごろから明治時代初期に染井村(東京都豊島区)の植木職人が桜を品種改良して作られた際に桜で有名な吉野山にちなんで吉野桜とされていました。
ただ、吉野山の桜は山桜であり別種でわかりづらいということから染井吉野と名前が付けられました。
ソメイヨシノが現在の東京都豊島区の染井村で誕生してから日本各地に広がった要因はなんなのでしょうか?
それは、ソメイヨシノが明治時代から街路樹として植えられるようになったことが発端とされています。
明治時代からですので、種の古さとしては大変新しい桜の品種となっています。
ソメイヨシノが全国に広がった理由としては花が綺麗なことはもちろんなのですが、花を咲かせてから葉をはやすに開花までにかかる時間が少なく、生育が早いことが短期間で有名になった理由です。
しかし、ここまで話をしてきたソメイヨシノはメリットばかりでありません。一つの個体からクローンで増やしてきたために病気への耐性が付いていなく病気に弱い性質も引継でいます。ソメイヨシノの弱さの例として、花見客がソメイヨシノの根っこを踏むためソメイヨシノが弱って枯れてしまうということがあります。
ソメイヨシノの特徴

ソメイヨシノは、花の展開に先立って花が咲きます。花弁の形は楕円形であり、大きさは2~3cm程度。咲き始めは薄いピンク色の花を咲かせますが、咲き進むと花の色は白くなります。一つの花につく花弁は5つ程度で一つの桜の木にたくさんの花が密集するように咲きます。
葉っぱの特徴としては、形態として細長い楕円形の形をしてます。葉っぱの淵は鋭いギザギザしており、葉っぱの柄に毛が生えています。

ソメイヨシノはサクランボはできないと思われていますが、実は少し結実性があります。ただ、ソメイヨシノにつくサクランボは食用ではなく観賞用です。一般的なサクランボよりも大きさは二回り以上小さいです。基本赤色の実ですが、品種によってはアメリカンチェリーくらい黒いものもできます。
ただ、ソメイヨシノはクローンでありソメイヨシノ同士では受粉することができないですので、実はできません。ソメイヨシノ付くサクランボは、別品種との交配種であると思われます。そのため、サクランボの色が赤や黒っぽいものがあるんですね。
|
|
木の形は横に大きく広がっていく傘状であり、開花時期は九州や四国などの温暖な地方では3月下旬ごろ。それからほどなくして関東や東北においても開花していく。
ソメイヨシノは昔から山に咲いている原種のヤマザクラよりも花が長く咲いているというイメージを持っている人が多いが、実際にはヤマザクラの方が開花している時期は長いそうです。このような誤解が生まれた理由としてはソメイヨシノがクローンのため開花時期がほとんど同時期であり九州から徐々に咲いていくことからだとされています。
ソメイヨシノの育て方
ソメイヨシノは私たちが桜と言われてイメージする最も一般的なものだと思います。それだけに多くの河川敷や学校などでも育てられています。
元々一種からのクローンであるために水切れや病害虫、外からの刺激に弱いという特徴が栽培難易度を難しくさせていますが、自宅の庭に夜桜を眺められるのは憧れですね。
それでは、明治にはいってから国策で全国各地に植えられるようになった日本を代表する花の育て方を見ていきましょう。
ソメイヨシノの育成方法
生育用土:ソメイヨシノは、水はけのよい土を好みます。鉢植えで植えることはそれほど多くはないかもしれませんが、鉢植えの場合は鉢庭石を忘れずにしてください。用土を配合する場合は赤玉土や腐葉土、砂利や川砂を混ぜてあげてください。水はけがよくなります。
肥料:ソメイヨシノは根っこが弱いので、それほど強くない化学肥料や堆肥を与えてあげてください。与える場所としては、根っこが弱いので直接与えないようにしてください。根っこは十分広がっていると思われますので、枝が伸びている場所の直下の地面に与えるといいとされています。
水やり:水やりとしては、それほど神経質になる必要はありません。一般的な植物と同じように土の表土が乾いたらたっぷりと与えてください。また、用土でも水はけのよい土にしていると思いますが、水の与えすぎで過湿になることはさけてください。根腐れを起こしてしまう可能性があります。
ソメイヨシノの基本情報

-
- 和名:ソメイヨシノ
- 英語名:Yoshino cherry
- 学名:Cerasus x yedoensis 'Somei-yoshino'
- 属性:バラ科・サクラ属
- ソメイヨシノの時期:多年草
- 開花時期:春先
- 花の色:ピンク色、白色
- 誕生花としてのソメイヨシノ:3月28日
そういった観点でソメイヨシノの寿命を考えてみると、ソメイヨシノは染井村で開発されたことからそれほど年数がたっていないこともありますが、高齢の木は他の種と比べると圧倒的に少ないとされています。ソメイヨシノの高齢樹が少ない理由としては、ソメイヨシノは成長が早いので老化もその分早いのではないかと考えられています。そのため一般的には寿命は60年程度ではないかと考えられています。高齢のソメイヨシノはないわけはなく実際に青森県には樹齢130年を超えるソメイヨシノがあります。ただ、このような高齢でも元気なソメイヨシノにするためには剪定管理をしっかりと行う必要があるようです。
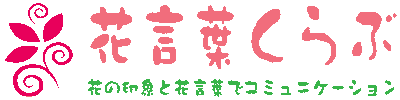







![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d5f6947.b1cb1fdf.1d5f6948.6960eac7/?me_id=1330097&item_id=10001463&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff063215-kahoku%2Fcabinet%2Fkudamono%2Fimgrc0100455646.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)