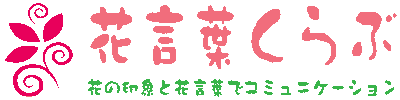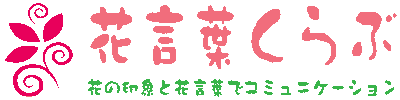カレーよそってあげるから食べようね。
カレーで一番好きなのはなにカレー?

うーん、カレーはノーマルのやつなのが好きなんだけど。
ライスはサフランライスが好きかな。

白米カレーに勝った!なかなか白米カレーライスが好きな人が多いのでこの勝ちは嬉しいゾ!

私、すごい!!
サフランの花言葉は?

鮮やかで華やかな紫色の花を咲かせるサフラン。スパイスとして利用されるのは花の中央にどんと構える雌しべで赤い3本の雌しべからしかスパイスは取れません。
綺麗な見た目を持ち、サフランライスなどにも利用されるこの花には、癒し効果のある香りもあり、昔から人々の生活をこれでもかというほど支えてくれています。
そんな人にとってなくてはならないサフランにはどのような花言葉がついているのでしょうか?
実際に花言葉を見ていきましょう。
サフランの花言葉は、
- 喜び
- 歓喜
- 陽気
- 愉快
- 節度の美
- 過度をつつしめ
- 濫用するな
です。
サフランの花言葉の由来は?

サフランの花言葉は「喜び」、「愉快」、「陽気」、「歓喜」、「節度の美」、「過度をつつしめ」、「濫用するな」というものです。
サフランは古来から薬用されてきており、その香りや滋養強壮効果があり、愛されています。また、黄色のサフランライスなんかは普段と趣が異なり、特別な感じがしてテンション上がりますよね(笑)
サフランには、鎮痛や鎮静、月経の誘発などの作用があるとされ、更年期障害の改善や月経困難、無月経、冷え性、生理痛などの予防や睡眠障害、頭痛の改善を図ることができます。このため辛い症状から改善されることの喜びなどが花言葉になり、「喜び」、「愉快」、「歓喜」、「陽気」などのポジティブな花言葉が付けられました。
人のために尽くしている感じがして好感が持てますね。サフランの薬用についてはこのあと詳しく記述しますが、生薬としての効能も高いです。
「節度の美」や「過度をつつしめ」、「濫用するな」という花言葉についてもサフランの薬用が由来になっています。
サフランにはストレスやイライラを改善するなど抗うつの効果もあるのですが、子宮の動きを活発にする効能もあり、接種しすぎるとかえって悪効果になってしまうことがあったり、使いすぎると神経が過敏になってしまい快楽に陥る中毒性があったりすることから使いすぎると危険ということで「節度の美」、「過度をつつしめ」、「濫用するな」という花言葉が注意文として付けられました。
納得の花言葉でしたね。花言葉自体に忠告の意味や効能を伝えるようなメッセージ性もあってとてもよく考えられていますね。
なかなかここまで利便性やメッセージ性の高い花言葉はないので、花言葉が付けられたのはそれほど昔ではないのかもしれませんね。昔に花言葉が付けられたのは何かとギリシャ神話から由来がとられていますからね(笑)
花言葉を知れば、その花の効能や歴史も垣間見ることができてとても面白いですよね。もし、他の花の花言葉を知りたい方は、下記ボタンより花言葉の本が買えますので、見てみてくださいね!
では、花名の由来についても見ていきましょう。
サフランの名前の由来は?
サフランは、古代から人類に愛されてきてその名前の由来は、アラビア語で黄色を意味する「ザフラーン」から名前が付けられました。
サフランの花は紫色で黄色はめしべの一部しか黄色くありませんが、なぜ花名が黄色というワンポイントカラーになったかと言いますと、サフランは染料として使用され、料理の色付けにも使われています。このサフランはカロテノイド色素というものを持っていて、水に溶かすと鮮やかな黄色になります。そのため食品や化粧品、着色料として利用され、黄色という意味の言葉が花名の由来になったのですね。
学名のクロッカス(Crocus)は、赤色のめしべが糸状に長く伸びることから、ギリシャ語で糸を意味する「クロコス(Krokos)」から名前が付けられたとされています。
このため、クロッカスは別名「春サフラン」や「花サフラン」などと呼ばれ、食用ではなく観賞用として楽しまれています。
サフランの歴史

サフランは古代より人類と共に共栄してきた植物で、その歴史はとても古く紀元前とも言われています。
その頃から香辛料や染料として利用されてきており、黄色の染料はとても貴重であったことから王族だけが使うことを許された高貴なる色だった時代もあるそうです。
最初にサフランの栽培を始めたのはスパイスの産地として有名なイランやインドのカシミール地方と言われています。
日本に入ってきたのは、江戸時代の末期で漢方薬として伝わりました。その有効性が確認され、国内でも栽培が始まり、1800年代には国産のサフランが目撃されるようになったようです。
サフランの収穫は開花時期である15日程度の間にひとつずつ手摘みで行われており、1本の花からとれるスパイスの量は非常に極小で1kgのサフランのスパイスを取るためには7万個の花を採取する必要があると言われ、世界一高価なスパイスとも言われています。
サフランは旧約聖書にもその記載があり、「芳香を放つハーブ」として記されています。旧約聖書にも記載されるほどにそのかぐわしい香りと少し苦みのある独特の風味は親しまれてきたのですね。古代ギリシャやローマにおいては、香水としてサフランが使用されてきました。サフランはとても貴重であるため、どばどばとは使うことができなかったでしょうけど、劇場や公会堂の床にサフランを散布し、香りを楽しんでいたと言われています。サフランを使うことで、身分の高さを誇示する狙いもあったのかもしれませんね。
東洋でも同様にサフランは香りの豊さから愛され、観客などをもてなし、歓迎するために来客者の衣服にサフランをふりかけ使用していました。
サフランの薬用
女性特有の妊人病の改善効果
サフランは日本では生薬として使用され、番紅花(ばんこうか)と呼ばれ、鎮痛、鎮静、月経の誘発作用を期待され、使用されてきました。サフランの薬用成分は子宮に作用することから、月経困難や更年期障害、子宮出血などに効果があるとされています。
日本同様に中国においても古くから生薬として親しまれています。
抗鬱・発汗作用
ストレスやイライラなど憂鬱な気分や抗鬱効果があり、それらの症状を押さえてくれるサフランですが、その精油にはサフナールという香り成分が含まれています。サフナールは少しの分量でもしょうがのように体を温め発汗を促す作用をもっているため、女性の冷え性など特有の体の不調を改善してくれます。
記憶障害の改善効果
さらに、マウスを使った実験も行われており、記憶障害を改善してくれるという効果があることが判明しました。これは大脳の海馬にある神経細胞に作用しているからです。漢方ではサフランが物忘れや認知症などの治療に利用されているのも納得ですね。
サフランの基本情報
花としての美しさとその芳香、効能など色々と約にたつサフランですが、その保存方法は、空気に触れないように密閉させ、乾燥した冷暗所に置いてください。香りなどは日光に当たると薄れてしまい、品質も悪化してしまいます。
それでは最後に、基本情報を見ていきましょう。
【基本情報】
和名:番紅花(ばんこうか)
学名:Crocus Sativus
英名:Saffron crocus、Saffron
別名:薬用サフラン
属:アヤメ科クロッカス属
原産地:地中海東部、西南アジアなど
開花時期:10月~11月
誕生花:11月4日
花色:紫色