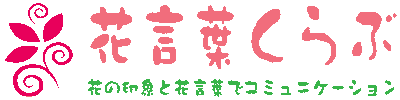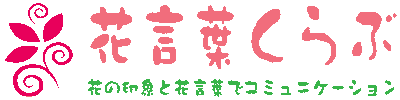マタタビ<silvervine>の花言葉

マタタビの花言葉は「夢見る心地」「晴れやかな魅力」です。
マタタビの名前の由来は?
マタタビの名前の由来は、疲れた時に甘い果実を食すると「再び旅ができる又旅」との意味だそうです。旅人がたちどころに疲労が回復して再び旅が出来たというかなりの疲労回復効果があるようですね。
ただ、実際の名前の由来はアイヌ語の「マタタムブ」からきたとされるのが有力のようです。アイヌ語では「マタ」は冬という意味、「タムブ」は亀の甲という意味で果実を表しているつけられたようです。

猫は口の奥の方にはヤコブソン器官と呼ばれる特殊な器官があります。この器官は人間は退化してしまいありませんが、「鋤鼻器官」(じょびきかん)とも呼ばれるこの器官は、主としてフェロモンと呼ばれる極めて微量な分子成分を感知する働きを持っています。そのため、揮発性のマタタビ酸に反応して猫ちゃんがダンスをしたり、じゃれたり、甘えたり、興奮するような変化が見られます。そのため、猫にマタタビと呼ばれるようになったようです。
マタタビ酸とは?(マタタビの成分)
猫がマタタビに反応する原因となっている物質をマタタビ酸と説明しました。そのマタタビ酸とは、「マタタビラクトン」、「アクチニジン」、「β-フェニルエチルアルコール」の三種類です。この三種類が猫と反応するようです。「β-フェニルエチルアルコール」は薔薇のような香りがします。
マタタビの特徴

マタタビは、山地に自生する落葉のつる性の植物で湿り気のある日陰を好みます。ツル植物ですが、巻き付くことは少なく、伸び上がってもたれかかり、垂れ下がるような生育形態です。
6~7月ごろに葉っぱが白っぽくなっていきます。その後、2cm程の梅のような白い花を下向きにつけ、咲き終わるころに葉の色が緑色に戻ります。
マタタビは3cm程のキウイに似た形の果実ができます。キウイもマタタビ科に属するから似ているようです。またキウイの枝や葉でも猫は酔うようです。
このマタタビは漢方にも使用されているようです。
|
|
マタタビの花が咲く前後に花の中心の子房に「マタタビノアブラムシ」という小さな昆虫が産卵します。卵を産み付けられた子房は、異常な発育をし通常の形と異なる形になります。形状としては虫こぶ状のものです。これを虫癭果(ちゅうえいか)といい、古くから人の漢方薬としても使用されてきました。
またマタタビは、山菜やおひたし、和え物、塩漬け、果実酒などにしようされます。果実として栄養価が大変高く、ビタミンCはレモンの10倍もあるとされています。
マタタビの基本情報
-
- 和名:マタタビ
- 英語名:silvervine
- 学名:Actinidia polygama
- 属性:マタタビ科・マタタビ属
- 開花時期:6~7月
- 誕生花としてのマタタビ:10月7日
- 花の色:白