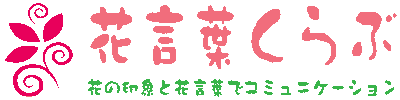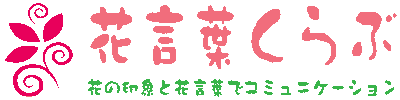畳の香りって独特ですよね。日本家屋といえば畳の匂いという人もいるぐらいですしね。でもよい香りと思う人と苦手な香りだと思う人どちらもいるようなんですよね。
たしかに感じ方は人それぞれですもんね。
皆さんは畳の匂いがお好きですか?それともすぐに消臭したくなりますか?
私は畳の匂いは清潔な感じがしてとっても好きですよ(^^♪
畳の匂いはい草の香りです。畳は部屋の中にある森と言われ、自然(森林?)を感じることができます。実はリラクゼーションの効果を持つ香りを出していて、なんとなんとい草のドライフラワーなんてのもあるんですよ!他の花を引き立てつつリラックス効果のある香りを出すなんてやるやつですね(笑)

い草(イグサ)の花言葉は?
い草は、暖かくなってきた時期に花を咲かせます。花の色は黄緑色で小花がいくつも集まって花を咲かせます。畳などの使われるい草は水辺に生えていて、水田で育つ香りのよい品種や、観賞用に草丈の低い品種などがあります。
では、そんない草の花言葉はなんでしょうか?
い草の花言葉は、
・堅く信じる
・従順
です。
日本人の和の心によく馴染む花言葉ですね。この花言葉から古き日本の大和魂や美学というものが感じ取れますね。
い草を知れば知るほど、畳や和室に愛着が湧いてきますね。

い草(イグサ)の花言葉の由来は?
い草の花言葉は、「堅く信じる」と「従順」でしたね!
日本人の武士道精神にぴったりな言葉だと思います。でも、どうしてこのような花言葉が付けられたのか?疑問ですよね。
調べてみたところ、「堅く信じる」と「従順」の両方に別々の由来があることがわかりました。
私が好きな方の花言葉である、「堅く信じる」の由来は、い草の枝分かれせずに花が咲く、蕾に至るまで硬い茎からまっすぐ一直線に伸びて、先っぽのとがった茎が束になっているようことから付けられているようです。また、い草の学名は「Juncus」といい、「結ぶ」や「縛る」といったラテン語から付けられています。これは、い草の茎で恋人たちは指輪を作り交換していたことから付けられています。この固く結ぶことができるい草の特徴からも「堅く信じる」という花言葉は命名されているのではないでしょうか。
また、「従順」という花言葉は、い草を女性が編む姿から付けられているのではないかと考えられます。古代の万葉集には、い草を編む大変根気の必要な仕事を薄情な恋人のためにイグサを編む女性の和歌が収められています。このことから、従順という花言葉が付けられたと考えられます。参考に実際の和歌を載せておきますね。
畳を編み込む作業と同じように、何回も何回も繰り返し、あなたが私の元へ逢いに来てくれたら、あなたと私の間にある道に邪魔な草が生い茂るようなことはなかったでしょうに
イギリスのエリザベス王朝時代に盛んに行われ、毎日い草は新鮮な新しいものに交換されていたようですよ!!
い草(イグサ)の基本情報
い草やアシなどの水辺に生える茎が強くしなやかな植物を編み込み、敷物やカゴ、帽子などに使用する文化はアジア圏に広く普及しています。ただし、日本では古墳時代からい草を編んでおり、畳というとても骨の折れはしますが、素晴らしい敷物が生まれる文化が発展していきました。

平安時代には貴人の座として供されていた高貴なる敷物を使ってみましょう。