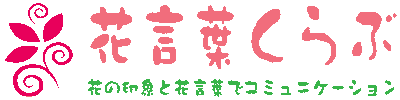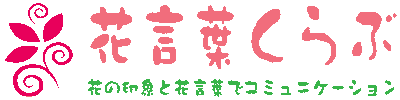秋の七草とは
秋の七草は、万葉集の時代から親しまれていた秋の季節の花についての短歌を由来にした、秋を楽しむための7種類の花です。
秋の七草の7つの花の種類と写真
秋の七草には7種類の花があります。名前と写真で紹介します。各草をクリックをすると、その植物についての詳細や花言葉、特徴などの個別ページにつながります。
萩(ハギ)
尾花(オバナ ※ススキ)
葛(クズ)
撫子(ナデシコ)
女郎花(オミナエシ)
藤袴(フジバカマ)
桔梗(キキョウ)
秋の七草覚え方の順番
秋の七草は、中学受験でも出題されることもあるようです。原文そのままの覚え方と、秋の七草の
秋の七草の原作短歌を語呂合わせなくそのまま覚える覚え方
「萩の花、尾花、葛(くず)の花、撫子(なでしこ)の花、女郎花(おみなえし)、また藤袴(ふじばかま)、朝貌(あさがお)の花」
「おすきなふくは」の語呂合わせで秋の七草を覚える
(オミナエシ、ススキ、キキョウ、ナデシコ、フジバカマ、クズ、ハギ
「はすきーなおふくろ」の語呂合わせで秋の七草を覚える
ハギ、ススキ、キキョウ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、クズ
秋の七草の時期
秋の七草の花の時期は7月、8月、9月、10月頃の時期で、昔の四季でいう秋の季節に当たります。
秋の七草何のために選ばれた?
秋の七草は季節の美しさを楽しむためにできたものです。
もともとは、万葉集に寄せた山上憶良の短歌で、秋の野原に咲いた7種対の花が本当に感動的だ!ということが謳われていて、それを現代も継承して秋の七草とされました。
変わる季節の美しさを7つの植物(花)で表現した偉人ですね。
秋の七草の由来となった万葉集の俳句・短歌とは
秋の七草の由来は万葉集にあります。学校の教科書でも名前が知られる「山上憶良(やまのうえのおくら)」が詠んだ2首の歌が始まりです。
「秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびをり) かき数ふれば 七種(ななくさ)の花」「萩の花 尾花 葛花 撫子の花 女郎花 また藤袴 朝貌の花」
現在、朝貌の花(あさがお)の花については、桔梗が当てられています。
秋の七草と春の七草の違い
春の七草は七草粥として食べるので知っている人も多いですが、秋の七草は食べられる草花とは違うのであまり知られていないですよね。
秋の七草はお粥にしないの?
春の七草は七草粥で食べますが、秋の七草は季節の美しさを楽しむというものです。
新・秋の七草とは
1935年(昭和10年)に、東京日々新聞社(現・毎日新聞)が当時の著名人7人から一つずつ秋の七草候補を挙げてもらって「新・秋の七草」を選んだそうです。
- 葉鶏頭(長谷川時雨)
- コスモス(菊池寛)
- 彼岸花(斉藤茂吉)
- 赤まんま(高浜虚子)
- 菊(牧野富太郎)
- おしろい花(与謝野晶子)
- 秋海棠(永井荷風)