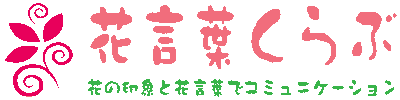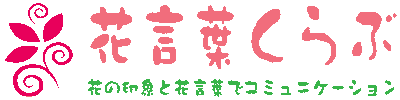フジバカマ(藤袴)の花言葉の花言葉
フジバカマ(藤袴)の花言葉は、「ためらい」「遅れ」です。
フジバカマの花言葉がためらい、遅れになった由来としては、フジバカマの花がゆっくり咲くためという説があります。
フジバカマ(藤袴)の基本情報
フジバカマ(藤袴)は、万葉集に出てくるくらいの昔から日本各地の河原などに群生していて、日本人に秋の花として親しまれてきましたが、今は数を減らしあまり見られなくなってしまいました。
別名として、中国では「蘭(らん)」と呼ばれています。蘭は別の花ですが、フジバカマも蘭もよい香りがする花なので、中国では区別するためにフジバカマは蘭草、ランは蘭花と書かれます。
-
- 英名:Thoroughwort
- 学名:Eupatorium japonicum Thunb
- 属性:キク科ヒヨドリバナ属
- フジバカマ(藤袴)の開花の時期:9月~11月
フジバカマ(藤袴)はレッドリストに入っている準絶滅危惧類
2007年8月レッドリスト。環境省レッドデータブックでは準絶滅危惧種に入っています。
アサギマダラ蝶(ちょうちょ)とフジバカマの花

フジバカマの花には、しばしば「アサギマダラ」という蝶々(ちょうちょ)が蜜を吸いに来ます。
なぜアサギマダラという蝶々が寄ってくるかというと、フジバカマの花の持つ「ピロリジジンアルカロイド」という成分がアサギマダラ蝶には必要で、アサギマダラ蝶のオスのフェロモンの原料になるそうです。
フジバカマ(藤袴)は秋の七草のひとつ
フジバカマ(藤袴)は秋の七草のひとつであり、秋の季語として多くの俳句に詠われています。
例えば、源氏物語(光源氏)では「同じ野の露にやつるる藤袴あはれはかけよかことばかりも」という句が詠まれています。
秋の七草とは
秋の七草の由来は万葉集にあります。学校の教科書でも名前が知られる「山上憶良(やまのうえのおくら)」が詠んだ2首の歌が始まりです。
「秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびをり) かき数ふれば 七種(ななくさ)の花」「萩の花 尾花 葛花 撫子の花 女郎花 また藤袴 朝貌の花」
現在、朝貌の花(あさがお)の花については、桔梗が当てられています。春の七草は七草粥で食べますが、秋の七草は季節の美しさを楽しむというものです。
萩(ハギ)
尾花(オバナ ※ススキ)
葛(クズ)
撫子(ナデシコ)
女郎花(オミナエシ)
藤袴(フジバカマ)
桔梗(キキョウ)